- おけさ柿日記
3月に催事が続き、ブログの更新が追いつかなくて… 。
遅れ遅れですが、メモとして。
2月27日。
佐渡の食材を使って食品加工を実践している人が集まった、パッケージングの研修会。
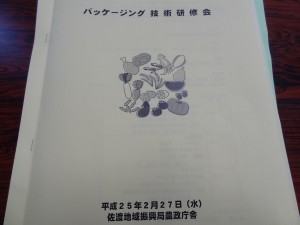
内容盛りだくさん
農産加工に関心のある、農業者を対象にした講習会だけに、講師の話を熱心に聞き入り質問も次々と。
具体的な事例を紹介しながら、基本技術の習得と新商品開発・販売力を付けるには…。
≪ 安全・安心な食品の提供 ≫ を、保健所の講師から。
・・・・・ 一番大切な基礎の基礎。
≪ 包装資材の基礎 ≫ を、パッケージング技術の実例を紹介していただく。
それぞれの袋の機能性についても、詳しくお話下さいました。
≪ 果実のシラップ漬けの製造 ≫ いよいよ、加工実習。
袋詰め食品の製造方法。 果実が丸ごと入った、店頭で見かける商品の出来上がり。

りんご シラップ漬け
研修会に参加するたびに嬉しいのは、熱心な先輩達が大勢いらっしゃること。
元気なこと !! 新参の私共を励まし、声をかけていただけること? (^O^)/

明るい講師 フムフム
佐渡地域振興局農林水産振興部 主催 でした。
いつも具体的で、楽しい勉強会の企画をありがとうございます。
雪が、畑を覆っています。 今日は青空がきれいな一日でした。
? ? ?
柿農家の方は冬の間に、木を剪定したり枝を整える作業をしています。
虫の棲み家となる木の表面を、数年置きにカリカリと削るのも冬の仕事。
こんな穏やかな日は、貴重な一日。 順調に仕事が進みます。

雪の柿畑
柿の話題を、もう、ひとつ。
先日、新日本風土記という番組で、丁寧に佐度が紹介されていました。
冬の佐渡沖が荒れるほど、寒ブリが集まり大漁となるそうで…… 登場するのが柿。

柿を網に入れ 寒ブリの大漁を かき 込む
鰤漁の初日には、たくさんの柿を網に投げ入れて、大漁を願うとのこと。
語呂あわせであれ、漁師さんの願いが通じて、柿が冬の寒ブリを網一杯に掻き込んでくれますように (^v^)
干し柿ファンのみなさま、お待たせいたしました !!
美味しい美味しい、おけさ柿の干し柿ができました(^u^)
噛めば歯ごたえしっかり、じんわり、ゆっくり、福よかな甘さが広がります。

おけさ柿 干し柿
干し加減のお好みは、いろいろですね。今は、しっとり少し柔らか目くらいの状態です。 “ もっと良く乾かした方が好き ” という方は、もう少し寒風に当てて待ちます。

きれいな干し柿 できました
ゆっくりと、時間をかけて乾かした柿ですので、
熱いお茶やコーヒーにも、相性抜群。 なめらかで、上品な和菓子みたいです。
柿餅の原材料となる、干し柿はどのくらいまで乾いているでしょうか?
冷たい北西の風が吹き始める12月から、じっくりと2か月間の時間をかけて、おけさ柿の干し柿は完成します。 今日は、親戚の干し場を見せてもらいました。
佐渡の冬は乾燥が弱いため、“ しびて~ぃ ” 風と、長い時間が必要になります。
その分だけ、濃厚でしっかりおいしい干し柿が出来上がります。

横に吊るして 順調に乾いています

縦に吊るして
吊るし方はいろいろですが、柿同士がくっつかないように、しびたい ( つめたい ) 風に当たるように、農家は苦心しています。
おいしい干し柿に仕上げるには、プラスの技術があるようで、作る人毎に異なります。
柿は冬の間に剪定を行い、6月に摘蕾、摘果。 草刈りを何度も繰り返し、防除を経て、ようやく10月から収穫が始まります。
干し柿にする皮むきと吊るしの作業は、「冷とうてだちゃかん」と言いながら、12月の作業。
少しでも風の通りがよくなるように、大型の扇風機で干し場に風を送り続けます。
柿の糖分が白く粉をふき、干し柿らしく色づくのは (^_^)/ もう少しです (^。^)
2013年、新年あけましておめでとうございます。
今年も、元気に過ごせて、田舎暮らしを楽しむことができますように・・・
ご近所の総社神社に、初詣に行ってまいりました。
今年も、佐渡の柿餅本舗をよろしくお願いします (^O^)/

真野、吉岡:総社神社

佐渡の柿餅本舗
2009年秋、佐渡へ移住。
「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。
最近のコメント
アーカイブ
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年


