- 田舎の味
ず~と待っていた、私でもできる近所の平場での、
山菜採りのシーズンが到来しました。
よもぎ と わらび と ゼンマイ 採りに、さっそく行ってみました。
今日は、実家の畑のまわりにある、軟らかいよもぎを摘んで、
初よもぎ餅を味見\(^o^)/

よもぎ餅
採りたてならでは、よく香り、さわやかで美しい色(^u^)

姉の家の畑で わらび摘み
薪ストーブを焚いた木灰でアク抜きすると、色よく、ヌメリが楽しい食感になります。
木灰はとても貴重品で、
友人に分けていただいたものを、たっぷりかけて(^-^)

ワタを被った ぜんまい
都会では、採ったばかりのゼンマイを見る機会がないそうなので、写真に一枚 (^。^)
天ぷらで、食べます。( ただし、採りたてのを少し‥ )

柿の若葉

柿 畑
遠くに菜の花畑

春の山
芽吹き始めたばかりの山は、まだ、淡い黄みどり色で、山桜も点在。

よもぎ餅
≪ 佐渡のよもぎ餅 ≫ のラベル そのものの風景が見えます。
季節が静かな冬籠もりから、活発な春へと動き出しました。
いよいよ、GWに入りました。
陽ざしの明るさの中、田植えの準備が進んでいます。
水を湛えた田んぼには、人やトラクターが出て賑やかに忙しそうになってきました。

田起こし と あぜの草刈り

フル回転 の 忙しさ
佐渡は急に、活気が出てきました。
朝には小鳥のさえずりで起こされ、夕方にはカエルの大合唱が聞こえる季節(^u^)
田舎暮らしはのどかだよ~。解放的な気分になれますよ~。
ですが‥
まだ寒さが残る日が続き、苗の育ちが充分でないとかで、
3 日に予定していた実家の田植えは、一週間先に延ばすことにしたそうです (>_<)
☆。。。。。。。。。。。。。☆。。。。。。。。。。。。。☆
佐渡おとなの遠足 外海府 と 真更川を歩く
ふり返りになりますが、4 月 23 日 ( 火 )
快晴の遠足日和
佐渡の北部に近い真更川を目指して、両津・北小浦地区から出発。
ドライブ距離が長くなりますので、体力のある男性が運転を担当して下さいました。
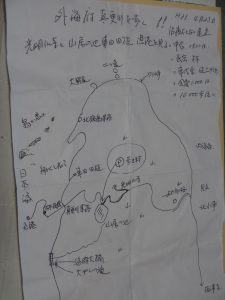
行程表
九品堂は、木食行道上人が住んで修行した跡地。

九品堂

銘さえ刻まれていない 丸い石が墓碑
木食は、火を通したもの ( 穀物 米・小麦・粟・稗ひえ・黍きび) などを食さず、
果物・山菜・木の実などのみで修行されたという。
車に乗って間もなく、また、止まれ止まれの合図。

佐渡の白キツネ
佐渡は、猿 熊 鹿 猪 などは棲んでいない、平和の地です。
ですが、春さなかのいっときだけ
白いキツネが、現れます ‥‥。
金北山の雪渓に、くっきり。
雪溶けが進み、( スリムな狐‥尻尾が大きめ )

旧北小浦小学校
ここは、沖の水中の岩場に棲むコブダイがよく知られています。
コブダイ見学のダイビングポイントまで、船が出される拠点となっている北小浦港。
永く君臨した弁慶からヤマトへ。 岩場のボスが交代したそうです。
いよいよ山へ入ります。

与六郎桜
佐渡随一と言われる与六郎桜は、推定樹齢 400 年とも、堂々とした山の主です。
今回の遠足の記念に、斜面に足を取られながらも写真を、
笑顔で一枚\(^o^)/
更に山の中の、光明仏寺へ。

南無阿弥陀仏
文字の先が尖った独特な彫りは、悪の因縁を絶つという≪刀剣名号(とうけんみょうごう)≫
奥深い山中で、穀物を摂らないで暮らすなんて、
木食弾誓上人の修業は、どれほど厳しいことだったろうと想像します。
その他にも、木食浄厳上人の名も教えていただいたのですが、詳しい関係はまだ不勉強です(>_<)

南無阿弥陀仏
この書体も、説明していただいたのですが‥(>_<)

山居の池 さんきょのいけ
山の中の、澄んだ水が豊かな大きい池。

山居の池 入り口
ここにも、刀剣名号の碑
池を一周し散策する予定でしたが、足元の道が細くてもろく、倒木もあり半周ほどで終了。
自然はゆったり穏やかに見えますが、無理はしないこと。 用心用心。
傍には、珍らしい草花がたくさん咲いていました。

白い?

薄葉細辛
「足元に気をつけてね」と、注意されて見ると、
葵の紋の形の葉っぱ、濃紫色の貴重な花が咲いていました。


「大岩かがみ」かな ?
長い山道を辿り、ようやく真更川の民宿「はやし」に到着。

さざえ あわび
海の宿らしいお料理がたっぷり並び、海藻いろいろ。

ワカメ ブリ しゃぶしゃぶで

ながも サラダ 煮つけ 卵焼き
さあ、また元気を出して。 午後の部出発。

車田植え の 田んぼ
ここは、車田植えの田んぼ。
今年は、5 月 18 日に古式にのっとって、三人の早乙女さんが丸く苗を植えていくのだそうです。

車 田
田んぼは、前方後円墳の形をしていて、北村さん個人の所有地。
持ち主の北村さんから、説明していただきました。
車田植えは、国の重要無形民俗文化財に指定されていて、
わずかに岐阜県高山と二ヶ所でのみ行われている、田植え習俗とか。
伝統を守ること、続けることに責任を感じていらっしゃるそうです。
毎年、テレビで紹介される行事。
ず~と、移動して
かなり急な山道を登ること 20 分くらい、下って 20 分。

関の大滝
鮮烈な山水が滔々と、滝壺に流れ落ちています。
木々も芽吹き始めていて、山はやさしい色。
今日は、 12,500 歩の遠足。
私にとっては、上り坂ありのかなり厳しい道のりでしたが、
それゆえに、満足度も十二分な遠足。
目で新緑を、沢音や滝に落ちる音を耳で。 贅沢な海の幸を、遠足のお仲間と。
昇り下りの坂を、頑張って歩いてくれた筋肉君達とともに
程よい疲労感を楽しんだ一日となりました。
後日
( 5 月 22 日 新潟日報 佐渡版 より )

車田植え
車田植えの紹介記事
田植えシーズンの終わりの吉日に、行われます。
佐渡の桜は、いよいよ終盤。
山の中の盆地にある、赤泊・川茂まで届きました。

旧川茂小学校の桜
花散らしの雨の後、花びらの絨毯。
毎月、第 4 木曜日の午後に ≪ かわもけんこう井戸端会議:会場 川茂会館 ≫ が、開かれていて、
25 日の、お花見の会に誘っていただきました。

お花見の会
地域のみんなと井戸端会議でつながりを作り、楽しみながら元気に暮らそうと立ち上がったサロン。
四月の例会日は、持ち寄った山菜を料理して、校庭の桜を眺めながらの昼食会という趣向(^u^)
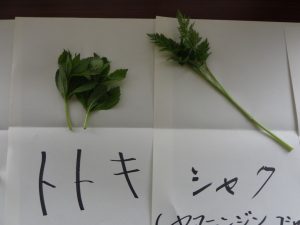
山菜 その 1
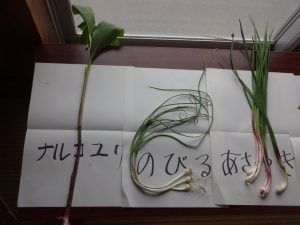
2
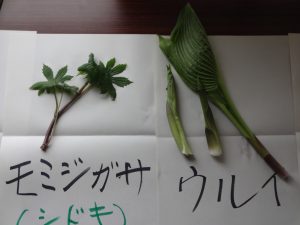
3

4
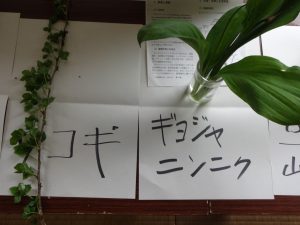
5

花いかだ


浜ぼうふう
山菜としてよく知られている、山ウド・こごみ・わらび・
セリ・ ぜんまい・よもぎ・タラの芽などの画像は、今回は省略。


さて、
朝、10 時に集合し、あ・うん の呼吸で、作業開始 です(^_^)v
集まった山菜を、女性陣が料理している間に、男性陣は会場の設営をします。

天ぷら
各種の天ぷら・草餅・栃餅・古代米おにぎりなどは、バイキング方式で取り分けます。
おひたしは、ごま味噌タレ・醤油マヨドレッシング・辛し醤油などで自由に味付け(^u^)



山菜の炊き込みご飯




わらび
山菜を味わえるのは、期間限定の山里の楽しみ。
賑やかに、手際よく、お母さん達の得意料理が並びました。
その他にも、サンドイッチ・きび団子をきび砂糖の蜜でなども。
メニュー豊富に集まりました(*^_^*)

生醤油
私たちは、先日搾った手作りの醤油をみなさんに味わっていただきました(^-^)
この、川茂の井戸端会議では、秋に開催される「かわも文化祭」にも、
農産物や手作り品のバザーを企画して、参加されているそうです。
元気なシニア世代が、地元の春の旬を味わう≪花見の会≫
身近な山菜のいろいろな調理の仕方や、昔の暮らしぶりを懐かしくお話するみなさんと一日。
貴重な植物を、たくさん知ることができました。
おそらくは、私たちが知る限りの
いちばん贅沢な≪お花見の会・山菜を味わう会≫に、参加させていただきました。
畑の端に植えっぱなしのチューリップが、花を咲かせました。
赤くつぼみがふくらんで、可愛いいようすに(^-^)

咲いた 咲いた チューリップの花が
(^。^)y-.。o○

並んだ 並んだ
(^u^) (^-^)
金北山の雪も、日ごとに溶けてきています。

金北山の残雪
春の山菜の王様タラの芽と、山ウドをいただきました。
タラの芽は、トゲトゲの木のテッペンにあって、素人には採れない貴重品。
ウドも、大きくなれば見えてきますが、土から芽生えたばかりでは見つけにくい山菜です。

ウド タラの芽
この春初めての、ふくふく丸いタラの芽、香りと苦みが魅力のやわらかいウド。
ウドは、ワカメとキュウリの酢味噌和えに。
タラの芽は、天ぷらで。
翌日には、ウドとタラの芽の天ぷらを作り、旬の椎茸を添えてミニ天丼にしてみました。
佐渡の山菜天丼セットで 、おいしく。
海老や魚がなくても、堂々とメイン料理と呼べる季節限定の一品\(^o^)/

春蘭
春蘭も天ぷらにして、食べる方がいらっしゃるそうですが、
珍らしい食材ではあっても、余りに貴重な花ですから、
眺めて楽しむ方が、好きです。
先日、種を蒔いた実家の苗は、順調に育っているようです。
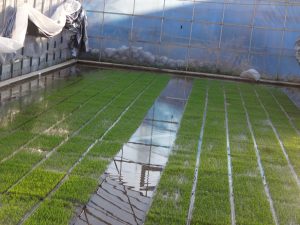
苗が出そろいました
強い雨の日もあり、寒さのぶり返した日もありましたので、温度の管理も細心に。
≪苗半作≫という言葉がある程で、苗の出来しだいで作柄が決まるという意味だそうです。
苗起こしは、大切な農作業の一つです。
佐渡に、やっとこさ春が来ました。
なにがあろうとも、毎朝、豆を挽いてコーヒーを飲むのが我が家の習慣です。

朝の一杯

朝はここから
佐渡に移住してから新たに習慣となったのが、玄米コーヒー≪黒焼き玄米茶≫

黒焼き玄米茶
佐渡に移住して間もない頃、先輩の家で初めていただいたのが、黒い色をしたお茶。
おだやかな、温もりのある味が伝わってきました。
「これは、どういうお茶ですか?」
『佐渡産コシヒカリの玄米を、土鍋で三時間炒った黒焼き玄米茶ですよ』
「初めて見るビジュアルのお茶です。ビックリです」
『 いろいろな本を読んで、手術後の姉にいいのではと思い、作り始めたのですよ』
『 体が温まってね。ウチでは、毎日飲んでいますよ』と、先輩。
「 私にも、分けていただけますか?」
『 ど~ぞ。 薬缶に水の時から入れて、ゆっくり 20 分~ 30 分くらい煮出して下さいね 』
その出合いから、もう九年が経ちました。
最初の頃、お茶を煎じる作業は時間を計ったり、ひと仕事をするという感覚でしたが、
毎朝の習慣になってからは、生活のリズムの中に。
そうして、幾度もお訪ねするうちに、
『 これからは、自分で作ってごらんなさい。先ずは一緒に作ってみましょうね 』
と、作り方を見学させていただくことに成った次第。
今度は、自宅でおさらい(*^_^*)
佐渡産コシヒカリ玄米 で 黒焼き玄米の焙煎を、始めま~す(^-^)

コシヒカリ玄米
ここまで、一時間です。
ゆっくり、ゆっくり、気長に。

まだ まだ
やっと、だんだん熱くなってきました。手袋は必需品です(^u^)
まだ、半ば。

もう少し
火を強めて。 しかし、焦がさぬように。

三時間
やっと完成しました\(^o^)/

冷まして 完成
火加減に気を配りながら、熱さに耐え、根気よく。

ポットに入れて
家では、いつでも、ちょっとずつ。
美味しいお料理も、続けば飽きてきますし、
健康にも体にいいものでも、覚悟が無ければ続かないのですが‥。
不思議なことに、なぜか続いたのです。

出かける時には、持参して
佐渡に住めば、コシヒカリ玄米はいつでも準備できますが、
黒焼き玄米茶にするまでには、ハードルがチョイと高めかも(^-^)
もし、興味がありましたら

黒焼き 玄米茶
どうぞ、飲んでみて下さい\(^o^)/
素にして上質な、
ぜ~んぶ佐渡産の、黒焼き玄米茶です。

佐渡の柿餅本舗
2009年秋、佐渡へ移住。
「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。
最近のコメント
アーカイブ
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年


