- 佐渡の行事
さわやかな、秋の気配がするようになってきました。
例年、9月の第一日曜日には、佐渡国際トライアスロン大会が開催されます。
トライアスロンの開催日は、ノーカーデーが定着しているため、
協力のためもあって、「しままるしぇ」は、営業を休みます。
☆。。。。。。。。。。。☆。。。。。。。。。。。☆。。。。。。。。。。。。☆
この日は、実家近くの先輩たちが誘って下さる鮎の石焼きの会に、お呼ばれしました。

鮎 焼き石にのせて
今日のメイン、石焼きの鮎。
内臓(うるか)と、自家製味噌で土手を作り、焼き石にのせます。

炭で 串焼き

天ぷら ゆっくり骨まで柔らかく揚げる

蕎麦 かりんとう

古代米入り お赤飯
朝、九時に集合し、料理と会場の準備を始めました。

竹串作り
片方の先を尖らせ、反対の端を土にさせるように切り込み、竹串を作る。

川から運んだ 石を焼く
穴を掘り、丸太を燃やし、近くの河原から集めてきた石を投入し熱すること2 時間。

串焼き

竹のカップ
竹の器で、佐渡の地酒をいただく。
大小の器に、どれにしようかな。子供のようにチョッと悩みながら選んでいました。

地酒の燗
竹の香りが移ります
さあ、準備が整って。 乾杯 (^O^)/

お世話役
この鮎の石焼きは、400年前から続くと言われる郷土料理ですが、
最近では鮎漁をする人が少なくなってきたことから、とても貴重な料理になっています。

串焼き うるか
仲間が集まり、呑むお酒は更に旨い

話と乾杯 盛り上がります
参加者の得意料理が、次々と登場します。

チャプチェの材料
さつま芋のでんぷんで作られた春雨と、野菜を、醤油、塩、砂糖で甘辛く味付け。
仕上げに、ごま油を加えます。

チャプチェ 完成

焼き茄子 枝豆 葡萄 漬け物

お地蔵さま の 広場
この集落の中央を流れる羽茂川。
そこに棲む鮎を愛でる、鮎の会。
この夏、50年に一度の大雨のため、川の濁りが治まらず、鮎の数も激減しました。
鮎の会の会員たちは会費を出し合い、
毎年、稚魚を放流し、鮎漁を通じて郷土料理として楽しむことで、
鮎漁を後世に繋ぎ、自然を守ろうとしています。
年に一度、お地蔵さまの広場に集まります。
会員の鮎に対する熱い志と、愛を感じた一日でした。
山菜を採りに、もう一度羽茂へ。
一週間前より、更にたくさんのワラビが採れましたので、
友人と親戚に少しずつお送りしました。
タケノコも頂きものがあり、食卓には、このところ山菜が続いています。
途中の山道が新緑のトンネルでおおわれていて。

山道の新緑

くねくね 山道

やわらかい色

ぼたん

モッコウバラ

藤
途中、伯母さんの家で庭を見ながら休憩をさせてもらいました。
季節ごとに、伯母の好きな色あいの花が咲いている庭。
新緑に包まれた山の自然に癒され、気分もリフレッシュできたドライブでした。
GWの土曜日、実家の佐渡産コシヒカリの田植えの日。
田んぼの田植え機の近くまで、苗箱を運ぶ手伝いに。
あいにくの冷たい雨降りとなりました‥‥(>_<)
でも、 甥が休日のこの日しか手勢が揃わないので、雨天決行することに。

田植え
稲の苗箱を、田植え機械に積み込んで、
さあ、スタート。

順調です
JA佐渡から、レンタルの田植え機を借りての作業。
数年前に機械が故障して以来、レンタルを利用しています。

助っ人 大活躍中
仕事の準備が始まれば、あとは順調にスイスイ進み
雨と寒さが少し堪えましたが、無風状態でしたので
田植えの条件としては、強い風よりず~と良いと考えて
辛抱とガマンの一日でした。

あけびの花
田んぼの畦道に見つけた、あけびの花に癒されながら(^_^)v
おかげさまで、無事に田植えを終了できました。
田植えの終わった田んぼに、水が満たされると
静かで、豊かさを予感させる、美しい風景が広がりました。
まだ、か細い苗ですが、植えられると淡い緑色が一面に。
佐渡産コシヒカリの“さなえ”さん、たくましく育ってね。
みんなで農作業をする時間は、実に楽しかった(^_^)v
お米の収穫の秋まで、おだやかな気候に恵まれますように。
年度が変わる時期。
今日は、一つの仕事の引き継ぎ、交代の手続きを完了しました。
地域に住めば、地域の協同作業やお役目が順番に回ってきます。
我が家は、昨年度の嘱託員としての役目を務めてきました。
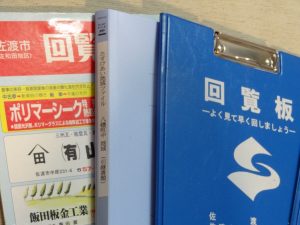
回覧板
八幡地区は、およそ100世帯ほどの集落ですが、
普段は四つの班に分かれ、班ごとに嘱託員が設けられています。
月に二回の回覧板配布、地区の道普請、運動会の手配、町内会費や寄付金の集金など‥。
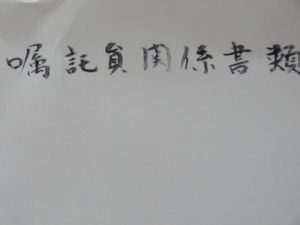
申し送りの書類
この家に引っ越して、まだ屋号もオボロにしか覚えていない頃から
「 来年は、お宅の順番ですよ」
近所の方々に言われていましたので、心の準備はしていましたが‥
手順がわからない‥。
配布書類をお届けに、何度伺ってもお留守だったりしましたが、
だんだんと、要領を覚えていきました。
我が家にも、親しみを感じてもらえるようになってきました。
嘱託員の地味な役目のことは、地区のみなさんが既に経験済のことゆえ
とても、親切に協力して下さいました。
おかげ様でこの一年の任期中には、特別な冠婚葬祭もありませんでした。
町内の方々が、平穏に健康で過ごされたことの証しでもあります。
今年度は、100戸の代表の町内会長と役員の大役を務める順が班にまわってきます。
2月半ばの夜、
引き継ぎの前に、我が家に集まり話し合いをしていただきました。
拘束される時間が多い町内会長の大役を、話し合いで穏やかに決めていただいたことに
ホッと安堵と感謝の思いです。
嘱託員や町内会長などの選出のために、
ご近所ともめ事が起きたり、町内会を脱会したりする地区もある‥とか。
一人暮らしのお年寄りや、固辞する方に役を無理やり押し付けたりすることなく
みなさんが役目を担い合える地区に住めることは、本当に嬉しいこと。
嘱託員の任務を無事終了して、地区の住人としてようやく迎えられたようです\(^o^)/
大雪と嵐の予報がでています。
数日は家に籠もれるよう、食料を買い置きしたり、灯油を継ぎ足したりして準備しました。
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
正月行事の締めくくりとして行われるのが、歳神様・・・せーのかみさま。
道路脇のあちこちで見かける、道祖神。
集落の堺にある小さな祠や石仏、村の守り神さま、実りの神様だそうで。
正月に家に来てくれた歳神様・・せーのかみさまを、お送りするために、
子ども達がその年の役宅に集まり、
「とうらいや」 さん の前日に、行なってきた行事だそうです。

歳神様
八幡町に住んで二年目になりますが、「 来年は、お宅が歳神様のお世話役ですよ 」
「 経験がないようでしたら、参考のために見ておきますか?」
‥と、今年の担当をしている、お隣さんが声をかけて下さった。
八幡町・中町には、ここ数年、子どもが住んでおらず年寄りばかり‥‥。
一年ごとの持ち回りで、この一式を預かるのだそうです。
床の間に、お神酒とお赤飯をお供えし、藁を両脇に置き、御幣を飾ります。

八幡町・中町の道祖神
正月のしめ縄や門松飾りを神聖な火で焼き上げる、
「 とうらいや 」 さんとは違う行事なのだそうです。

玄関に旗 せ~の神の当番
せ~の神の行事を伝えているのは
この八幡町と隣の集落の数か所くらいに、なってしまったのだそうです。
飾りの藁の意味などを、きちんと説明がしきれない覚束さもありますが
それ故に、覚え書きとして
写真を撮らせていただきました (*^_^*)

佐渡の柿餅本舗
2009年秋、佐渡へ移住。
「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。
最近のコメント
アーカイブ
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年


