- 佐渡の行事
毎年、6 月の第 2 土曜日に公演されている、「おんなたちのこころみ」
6 月 8 日、6 時 30 分より、開演。
金井能楽堂に、観に行ってきました。
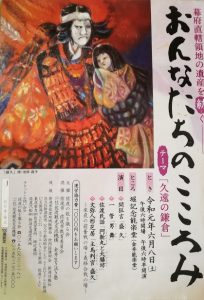
毎年、会を重ねて今回で15 回目の公演となるそうです。
演目は
間狂言 「盛久」 ( 大蔵流 )
一 管 「男舞」 ( 一噌流 )
佐渡民話 「阿新丸と大膳坊」 ( 佐渡民話語り部の会 )
文弥人形芝居 「主馬判官 盛久」 ( 常盤座 )
主催は、佐渡の能を識る会
普段はなかなか観ることができない、演目ばかりです。
佐渡文弥人形芝居が、国の重要無形民俗文化財の指定を受けたのが昭和 52 年。
平成元年に、本間照代さんが初代の代表となって、文弥人形芝居の仲間を誘い、
女性ばかりの一座<常盤座>を旗揚げしてから 30 年目となるそうです。
奥の深い芸能の世界を、楽しく。
若手を育てながら、伝え残したいと活発に活動されています。

この記事は、公演の前日、
新潟日報に紹介されていたもの。
この夜も、激しい動きで人形を遣いながら刃を交え、
合戦の場を盛り上げ、
太夫の爪びく三味線の音は、低く情緒たっぷり。
じっくり聞かせる語りは、
引き込まれる程に聞き入ってしまう、味わい深い公演でした。
田植えの日、みごとな五月晴れに恵まれました。
清々しさに、気分も背筋もスーと伸びてきます。
よ~し、やるぞ。
老兵なれど私たち、手伝いネコの手部隊は、実家へ (^。^)

田植え 一枚目の田んぼ
山は、まだ淡い芽吹きの色

棚田
田んぼはどれも、田植えの準備が整っています。
佐渡の稲は、広い平野ばかりでなく、
このような小さな規模の、棚田で作られることが多いのが実情。
山からの水を運ぶ 江 には、勢いよく冷たい水が流れています。
この山からのきれいな水が、おいしい米を育てます。

田んぼからの移動
田んぼから次に移動する時には、特別な注意が要ります。
後ろにばかり重さがかかり、前方が浮いてしまうとバランスが崩れ、
転倒してしまう事故も起こります。
そこで、
田んぼの畦から安全に移動する時には、前に人が乗って重石となります。
技術はなくても出来るお手伝い。これもその一例。

稲の苗箱
稲の苗箱を運ぶ
苗箱は、苗と水分をたっぷり含みます。
特別な重さではないのですが、
お陽さまの下で一日、中腰で苗箱を手渡しを続けることは、ジンワリと腰にきます(>_<)

近くの土手に つつじ
お茶で水分補給をマメにしながら‥ 柏餅でおやつ休憩をとりながら‥ 腰を伸ばしながら(^u^)
田植えは、農家にとっては特別な日。
ベストワンの、ちょっと楽しみな日でもあります。

つばめ
身のこなしの軽いツバメのおしどりが、見守ってエールを送ってくれます。

変形の田んぼ
どう機械を動かすか、動線を考えて植え付けていきます。
おかげさまで無事に、田植えを終了できました。
ほッ。 安堵と感謝の思いです。
まだ、か弱い苗たちですが、直ぐにシャンと根を張ってくるでしょう。
農薬・化学肥料を 5 割以下に減らして育てられる、
特別栽培米・佐渡産コシヒカリが植えられた、淡い緑色のかわいい苗の列を
美しいなぁ、といつも思います。
日本穀物検定協会による、米の食味ランキングで、
連続 14 年も、特 A を獲得している佐渡米の田んぼはここにもあります。
家族が食べるおいしいお米は、自分で育てる。
農業への基本の思いは、この一枚一枚の田んぼにあります。
気温が低めの日が続いたせいか、田植え作業が若干遅くなっているような気がしますが、
田んぼに水が張られた風景は、静かで、美しいな~\(^o^)/
おだやかな天候に恵まれて、スクスク育てよ。
雨にも風にもちゃんと耐え、逞しく順調に育てよ‥と、願っています。
快よい疲労と、達成感で夕方を迎えることができました。
いい汗をかきました(^。^)y-.。o○
今日は、成人の日。
無風で明るい陽ざしにあふれ、真冬の佐渡とは思えないほど (^_^)v
正月の行事を締めくくる、どんど焼きの煙が、あちこちから立ち昇っているのが見えました。
八幡町では(とうらいやさん)と言っています。
正月飾り・注連縄・下げ紙・子どもの書き初め・などを持ち寄って、竹を組み焼き上げます。
両津の住吉の先輩をお訪ねした折りには、どんど焼きの準備中でした。
私の実家のとも、住んでいる八幡町のとうらいやさんのとも、まるで異なっていました。

正月飾り 注連縄など
まとめて、束ねて。

ふくろ さいふ
家族の一人ずつのフクロ を作り、結婚して家を出た娘さんの分も用意されているそうです。
親心 (^O^)
袋 の底には、家族のひとり毎に色を変え、五色のテープで飾りつけ、
財布 には、今年の願いを墨で書き込んであります。
そして、一本の竹の枝に女性はフクロ、男性はサイフを飾り付けます。
「 嫁に来たばかりの時に、姑さんに作り方と意味を教えられて以来、
自分の役目として、続けて来たのよ 」
みんなの無病息災、家内安全の願いを込めて。
どんど焼きは、大切な行事なのです。

昨年の竹と 今年の竹
昨年の竹をどんど焼きで納め、神聖な火で清めた竹を持ち帰り、玄関に飾るのだそうです。

今から どんど焼き会場へ
飾りを付けた竹を担いで、子ども達が張り切っています。

どんど焼き の 煙が‥
遅くなってしまい、あちこちから上がっていた煙が‥
これだけに‥なってしまいました‥。
所が変われば同じ佐渡の中でも、風習がこれほどにも異なるなんて。
ビックリ\(^o^)/
どんど焼きの火で、餅・するめ・昆布などをあぶり、家に持ち帰り家族と分け合って食べます。
どんど焼きの火が勢いよく燃え上がると、今年の豊作も占えるのだそうです。
この一年が、穏やかで心安らかに過ごせますように、と祈ります。
冬なのに、冬らしい天気にまだならない。
機会ある毎に、「みんな集まって、賑やかに旨いものでも食べよう」と誘っていただき(^O^)
今回は、自然薯 (山いも)を食べる会。
山いも掘りは、深く深く掘って掘って、根気のいる作業と聞きます。

自然薯
名人が掘り上げた、みごとな自然薯。
壁に吊るして、然るべき時が来るまでは、オブジェとして楽しんでいます。

あぶらめ
自然薯の出汁には、アブラメの濃い味と香りが似合うのだそうで、焼いて干して。出番待ち。
さて、後日
役者が揃ったところで、山いも・麦とろの会\(^o^)/

絵に、姿を残して
いざ、
山から掘り出した「山いも」というところに価値がある、本当の自然薯。
みんなで、ご馳走になります(^u^)

大宴会
山いもの汁が、のびないうちに、いただく(^-^)

山いも 麦飯
アブラメの出汁でのばした味噌味に、山いもと麦飯。
山いもの天ぷら、山いもの炒めもの、里芋のポテトサラダなどなど。

鳥汁
お祝いの席には鳥汁。 アツアツのうちに、いただきます (^O^)

鰤の刺身
今日は、佐渡の北部の鷲崎漁港では、“ 寒ブリ大漁祭り ” が、開催され賑わったそうです。
佐渡の冬の魚と言えば、鰤。
会場は、先日オープンした八幡町の古民家、優游亭にて。

古布・山葡萄の蔓・アケビの蔓・こぎん刺しの布など、手仕事のバックなど。

器 小物

布 小物

上にも 展示品あり
小物があちら、こちらに。 楽しく探したり、鑑賞したり (^_^)/

柿餅本舗のコーナーも、一角にあります(^-^)
これ以上の贅沢はあるのかしら、と思いたくなるような、陽気な宴でした。
米作りの最終作業は、米摺り。
天気の良い日と、人手の揃う土曜日を選んで、作業を手伝いに実家へ。

籾ガラの山

助っ人たち
機械の動く音や、流れる籾の動きを見守る助っ人君たち。

平成30年度 佐渡のコシヒカリ新米
GIAHSに認定された、米作りの島のお米

コシヒカリ玄米
出荷を控えて、最終作業の袋詰め

認証米のマーク

米摺り 終了
米摺りを無事完了\(^o^)/
今年は、夏の苛酷な暑さが続き、お米の収穫量に影響が出たそうですが、
家族が安心して毎日いただける、お米が出来ました。
新潟県のお米は、魚沼産のコシヒカリが有名ですが、
佐渡のお米は、食味試験で「特A」を維持し続けていることをご存じでしょうか?
実家のお米も山あいの、お水のきれいな田んぼで作られている美味しいお米。
私たちは、農作業の忙しい時や、人手が必要な時にだけ手伝いに参上する、
農業は素人の助っ人ですが、収穫が無事にお終えられたことに安堵しています。
おかげさまで、
我が家の飯米一年分、佐渡産コシヒカリを分けていただきました\(^o^)/

佐渡の柿餅本舗
2009年秋、佐渡へ移住。
「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。
最近のコメント
アーカイブ
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年


