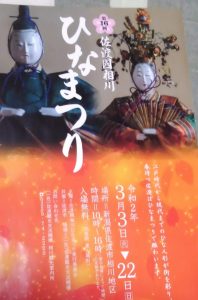- 佐渡の行事
梅雨が明けたというのに、昨日も今日も雨。
お昼のメニューは素麺にすることにして、茗荷を探しに畑に。
出ていました、ふっくら茗荷。
雨が続いたので、いつもより早めに、いつもより沢山でていました。
青紫蘇と生姜もたっぷり薬味に添えて、さわやかソーメンをいただきました。
こぼれた種から、勝手に生えてきた青紫蘇。
薬味が畑にある、しあわせ。
茗荷はまだ、たくさんありますので、梅酢に漬けて保存しました。
冷奴の薬味にも、お稲荷さんや寿司に刻んで入れても食感が楽しめます。
香りのパセリも、乾燥して保存。
ポタージュスープに少し浮かせたり、サラダドレッシングに混ぜたりして色と香りを足しています。
沢山はいらないけれど、少しだけでも欠かせないのが香草。
去年は冷凍してみたのですが、乾燥した方が使い勝手がいいようです。
ささやかな、ささやかな畑の恵みに感謝、ありがたい。
今日はまた、大嵐です。
暦の上では、啓蟄となりましたが、
アラレが降ったり、ザッと雨が強く降ったり、パッと晴れ間がのぞいたり。
新年度の神事の一つである、“ 倉谷の大わらじ” が、新しく変えられていました。
大わらじを掲げる意味は、
「集落には、こんな大わらじを履く大男が住んでいるぞ~」
外から入り込もうとした盗賊が、逃げ出したと言われる
疫病や悪人除けの、道祖神だそうです。
羽茂・締め張り地区で作られている藁の馬。(締め張り馬)
我が家の小さな守り神。
尻尾が真っすぐ伸びて、疾走しているようすを表しています。
締め張りでは、地区の結界を示す意味で、
人が通る道の頭上に、しめ縄のように藁の馬を張ります。
大わらじと同じように、集落の魔除けを願う道祖神だそうです。
我が家の締め張り馬は、土産用の工芸品ですが、
同じ作り方で、早刈りの稲の芯で作る
美しい守り神。
今では、締め張り馬を作る方が高齢となったため、
後継者を育てることに、力を注いでいると聞いています。
地域を守る道祖神は、形いろいろ。
思いは、同じ。
今日は、ひなまつり。
佐渡國相川 ひなまつりが始まりました。
新型コロナウイルスの、感染が全国で広がっていることを受け
佐渡でも、イベントが次々と中止、延期、変更されています。
相川の町のお雛さまを見ながらの、散策を楽しみにしていたのですが‥。
お茶会 (ホテル万長) (きらりうむ佐渡)
田村優子さんのコンサート
お雛さまの出展中止 (松榮家) 他 も中止に。
急な変更ですので、住民にきちんと伝わっていないこともありそうです。
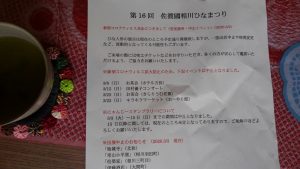
3/2付 変更のお知らせ
お雛さまを拝見に、彩花・森さんへ
天井から、遊び心がいっぱいの手作り古布の作品
お雛さまの公開初日
相客の方と、お茶をいただきながら楽しくおしゃべり。
沈んでゆく夕日が、目の前に広がる窓だそうです。
羨ましい眺め(^-^)
早春のひと時、たくさんの可愛いお雛様に囲まれて、
相川の町の歴史を、色々教えていただきまた。
今日から二学期が始まり、通学路に子供たちの元気な声が戻ってきました。
☆。。。。。☆。。。。。。☆
旧歴の7月23日24日に、行われてきた地蔵盆の行事があります。
街角のお地蔵様にお供え物をし、
町内の安全や、子供たちが健やかに育つことを願っての伝統行事です。
23日朝には、当番さんとお堂の清掃。
そして夜には、地蔵堂に集まりお念仏を唱えました。

地蔵念仏
トントンと太鼓を打ち、チンチンと鐘を叩き念仏を唱えます。
来年は初めて、お世話係を担当しますので、
準備の仕方を教えていただきました。

お供え 団子
高坏に20個のお団子2組。 10個のお団子を5組。

花台
飾りの幕を張り、お花・ロウソク・線香・お菓子・山盛りのご飯・お水など。

お坊さんにお経をあげていただく
24日 朝には、お坊さまを待ちます。
持参された御幣・お飾りしていただき完成。
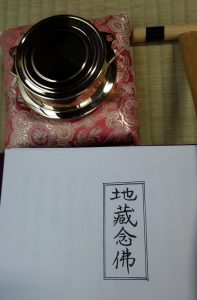
鐘 地蔵念仏

入口に 鈴
お団子の手配・お布施・お花の準備も忘れないように。
メモメモ( ^^)
子供たちの健やかな成長を願っての地蔵盆ゆえに、
お菓子の準備もするのだそうです。

のぼり旗
わが集落は、家の軒数が年々減ってきて、
年寄りばかりが住む街並みとなりつつあります。
若い世代の参加が少ないのが現状です。
身近に寄り添い、
住人の祈りや願いに耳を傾けてくれるお地蔵様。
「続けられる時まで、地蔵盆を続けられるといいね」
お道具を片付けながらの会話でしたが、
さて、いつまで続けることが出来るのだろうか・・・。
佐渡の 6 月は、能の公演のシーズン。
6 月 12 日 の牛尾神社へ
新穂・潟上にある、牛尾神社能舞台の奉納薪能を初めて観に出かけてきました。

のぼり旗

参道

本堂に参拝

境内の大杉は、安産杉と呼ばれています。

能舞台

薪に点火

夕闇の篝火
かがり火が灯され、いよいよです(^-^)

例祭宵宮奉納薪能
演目は、「 半蔀 はしとみ 」

夕顔の花の化身
京都・北山の雲林院に住む僧の、夏の夜の夢でした‥とさ。
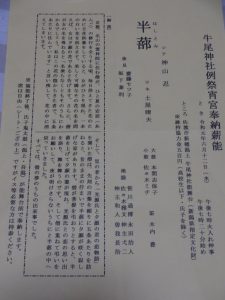
番組
演能の終了後には、氏子による鬼太鼓が二組、( 潟上・吾潟 ) 奉納されました。

鬼太鼓
能舞台前にて演じられた、奉納鬼太鼓。

鬼太鼓
牛尾神社の例祭を祝っての、宵宮奉納の薪能と氏子鬼太鼓。
丁度いい具合に月がかかった宵に、ござに坐って、
かがり火の煙と、薪のはじける音を聞きながら、能を楽しみました (^O^)

佐渡の柿餅本舗
2009年秋、佐渡へ移住。
「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。
最近のコメント
アーカイブ
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年