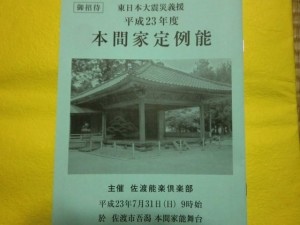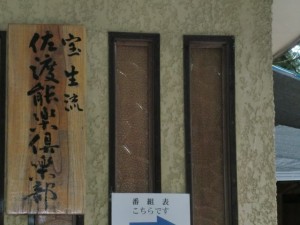- 佐渡の行事
佐渡の夏の祭りとして盛り上がりをみせる、アース・セレブレーション。
和太鼓集団『鼓童』が、毎年城山で公演を続けてきました。
鼓童が世界を回って公演し、その魅力に惹かれた多くの人が、夏の佐渡に集まって24回目の祝祭。
太鼓のリズムが、心と胸を高鳴らすのは世界共通のよう。
港の広場では、テント村が立ち並ぶハーバーマーケットが賑やか。
自然の色にこだわり続ける、旅する染物屋さん。
チェーンソーで作った、可愛い兎の木ぐるみ(?)のお出迎え。
かき氷屋の店員さんは多国籍。ワールドワイドでワイワイお手伝い。
柿つながりで、「只今店主散歩中」。ボッテガ・サドのお店。
佐渡に古くから伝わる民芸や陶芸を、さらに田舎風にアレンジ(?)かな。
思わずほのぼの、のお店:古食庵。
中央広場では、ライブを待つ人たちが、の~んびり、の~んびり。
佐渡の宝生流の能を代表する本間家。
本間家が所有する能舞台で、7月の定例能が催されました。
18代目のご当主は能楽師です。
最後の演目、船弁慶をゆっくり観ることができました。
朗々と豊かに響く地謡の声。
笛・小鼓・大鼓・太鼓の息の合った掛け合い。それに舞いが加わり、能って楽しいなと思える時間でした。
演者達も自由なセッションを楽しんでいるよう。
ず~と昔。祖父が能が好きでしたので、NHKラジオの “邦楽の時間” を聞かされていた時代があります。?
流派の区別もつかず、謡の意味もわからない、50年も前の子供の頃。
風呂の湯加減がいい時には、水面を打ちながら謡だした、爺さまを懐かしく思いだしました。
佐渡・真野地区に永く伝えられてきた文弥人形、真明座。(島内には他にも座が活動中)
公演前には、演目の内容の説明がありました。
真野大神宮のまつりは、麦飯まつりとも呼ばれています。
(昔は麦の収穫後の祭りだったので…。今は麦が黄金色に波打つ風景は見られなくなりました)
文弥人形が演じられる夜には、集まった町の人たちに“麦飯の握り飯”が振る舞われたそうです。今もその形が伝えられています。
女性の太夫の味わいある声と、節まわしの良さ。
人形を使う人の、立ち回りの小気味よさ。 話に引き込まれました。
伝統芸能を受け継ぎ、次の世代に伝えるには、根気よく繰り返しの稽古を怠らないことが大切だそうです。
佐渡の文弥人形は、国指定重要無形民俗文化財としての認定を受けており、誇りと責任を持って研鑚を重ね、演じられています。
真明座の座長である川野名さんは、後継者を育てる為に、地元の中学校の部活動を熱心に指導されています。
個人の庭の花や庭木を一般に開放する、オープンガーデンが西三川にあります。
ゆっくり散歩をしながら、香りを楽しみ色とりどりの薔薇を見ることができます。
本業はりんご園の“さかや農園”さんです。
りんご畑の緑の中で、それぞれの花の色が更に引き立ちます。
イギリスでは、このようなオープンガーデンが盛んとのことです。ゆっくりと巡る贅沢な時間でした。
普段の手入れはさぞ大変では?と思うのですが、「楽しみですから」とさらりとおっしゃいます。
ご夫婦でお茶のサービスまでしてくださり、バラの公開を始めてもう十数年目になるそうです。
羽茂祭りの一日。小さな町に濃縮された伝統の芸能文化が満載。
幼稚園児から若者、女性の踊りまで、音と踊りでみな参加の豊かな土地柄です。
この夜は、冴えざえとした月夜でした。
蛍が飛びかい、薪能がさらに幻想的な雰囲気となり楽しめました。

佐渡の柿餅本舗
2009年秋、佐渡へ移住。
「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。
最近のコメント
アーカイブ
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年