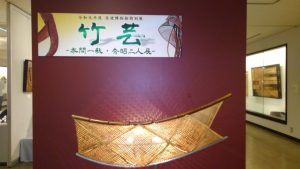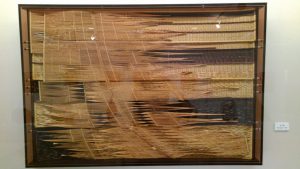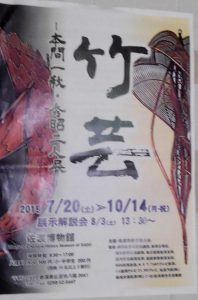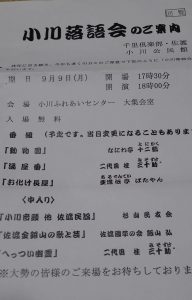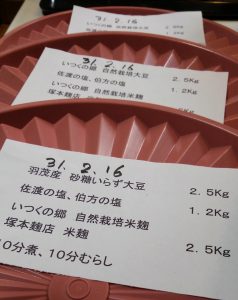- おけさ柿日記
佐渡の国仲平野の稲刈りは、ほぼ八割ぐらいまで進んだよう。
トンボが羽を光らせて、刈り終えた田んぼの上を飛び交っています。
☆。。。。。☆。。。。。☆
佐渡の竹工芸の第一人者である
本間一秋さんと本間秀昭さんの二人展が、
佐渡博物館で 7/20~10/14まで、特別展示されています。
さて、ここから
竹を通して光の表情を楽しむ、会場の入口
大作がたくさん展示されている中に
向きを変えると、細い竹では小文字で‥a b c‥に。
遊び心にフフッ(^-^)
壁面の装飾
いろいろな角度から、不思議な展開
光の具合で、金属のようにも見える屏風
古民家の屋根裏で、囲炉裏に燻されて数百年の味わいある竹
貴重な煤竹(すすだけ)をいかして
根気と技術
師であるお父様の一秋さんは、2017年にお亡くなりになりましたが、
お二人の作品が一堂に集められた、貴重な親子展です。
この曲線のために、幾度もあぶったり、竹が割れたり‥したとか。
壁には、色紙掛け・短冊掛け
本間一秋さんと秀昭さんは共に、日展の竹工芸部門で
特選を2回受賞されてるいる第一人者。
国内外での個展を開催されたり、
国外の美術館に、作品が多数収蔵されています。
秀昭さんは、日展はじめ日本現代工芸美術など主要展示会へ出展。
受賞歴多数。
メトロポリタンやボストン美術館に、作品が収蔵されています。
高名な芸術家ということを忘れてしまうほど、
気さくな方です。
作品には、自由な精神と深さを感じます。
作品は、自由に撮影 OK
佐渡博物館は、展示期間中は休まず営業。
佐渡の竹で、美術工芸を生み出した親子の二人展。
今回は107点もの作品が、特別展示されています。
展示が終了すると、竹工芸の愛好家のもとへと
作品の多くが、海外に渡ってしまうことが決まっているそうです‥。
今までに2回、観に行っていますが、
今のうちに、もう一度楽しく拝見したいと思っています( ^^)
金木犀の香りが、どこからか漂ってきています。
秋晴れの日が続き、佐渡は稲刈りが進んでいます。
ススキの穂が青空に輝く今日は、稲刈り手伝いに実家へ。
外の作業が、とても心地よいこと!(^^)!
風に、稲穂がサワサワと音をたてて揺れ
藁の甘い香りが、あたり一面に漂っています。
黄金色の、佐渡産コシヒカリです(^-^)
酷暑の夏の影響が、お米の出来に心配されているそうですが‥
田んぼは固くて、順調に刈り取りが進んでいます。
米粒の育つ時に高温が続き、結果として米粒が小さ目の傾向とか。
四回に分けて、稲刈りと乾燥。
農薬を減らし、草刈りを繰り返して育てた、佐渡産コシヒカリ。
八十八の手数をかけて、清い山の水で育ったお米の収穫。
今日が最終日。
安堵と感謝の日です。
男達が稲刈り作業の間に、私は榧(カヤ)の実を拾いました。
稲刈りの頃には、ちょうど榧の実が拾い頃。
アッと思う間に、箱に一杯になりました。
緑色の外皮からは、
爽やかなすっきりした香りがたってきます。
緑色のカヤの実を土に埋めて、乾かないように腐らしてから
実を洗い、乾かして、保存します。
冬場のおやつとして、お婆さんがホウロクで炒ってくれたのを思い出します。
香ばしい、和製のナッツです。
榧の木は、300年経ってやっと成木と言われるほど、
ゆっくり、永い時間をかけて成長するそうです。
佐渡の南部は、敷地の片隅に榧の木がある家が多く残る地域です。
ちなみに、600年を超える老木を有する、徳和地区の大椋(おおくら)神社は
佐渡市指定の記念物として、大切にされています。
春の田植えと、よもぎ摘み。
秋の稲刈りと、榧の実拾い。
田舎暮らしの素朴な楽しみです( ^^)
私たちは、この10月で佐渡に移住して10年となりました。
佐渡に移住する前から、
何かと親身に相談にのって下さっている先輩がいらっしゃいます。
その方が呼びかけ人となって、「小川落語会」を立ち上げられました。
地区の公民館で楽しめる“落語会”です。
9月9日 18時より 地区のふれあいセンターにおいて。
今回で6回目を迎えます。
当日は、台風15号が迫ってきており
落語会に出演予定の噺家さんが、新幹線が運休となった為
佐渡に渡れなくなったという、ハプニングも発生。
あれやこれやと、変更に変更を重ねながら
ともかくも、スタートしました。
落語 「動物園」 なにわ亭 十二鶴(とにかく)さん
急遽の出演依頼に応えて
平腰忍さんによる 一人芝居 「石地蔵」
夏目漱石の「夢十夜」から。
お話を聞いていくうち、ちょっとゾ~とする結末へ展開。
圧巻の世界へ、引き込まれます。
落語 「お化け長屋」
ばたやんさんは、二席となりました(^-^)
「佐渡金銀山の歌と芸」 飯山弘ご夫妻による歌とハーモニカ
地元の小川地区に伝わる
小川甚句と小川音頭の披露がありました。
観客のみなさんからも、手拍子が加わり会場が和やかに( ^^)
小川の地名を冠した「小川甚句」の
三味線・太鼓の快い響きや
踊り手の身振り手振りに、ついつい気を取られてしまい
歌の内容を聞き取れなくて‥。
祝い唄なのか、労働歌なのか、神仏に豊穣を願う歌なのか‥。
前日には、地区のみなさんが草刈りをし、駐車場を整えたり、
当日は、受付から舞台や客席の設営を分担するなど
小川地区を挙げての大きな行事になっています。
回を重ねる毎に、出演者と観客との温かいふれ合いトークも
なごやかに交わされて、
地元の会場ならではの、ほのぼのとした落語会になりました。
秋の爽やかな空気が、うれしい毎日です。
遅くなってしまいましたが、味噌の天地返しをして、
美味しく育っているか‥味見をしてみました。
なんか、いい具合!(^^)!
静かに熟成して、おだやかな甘み・うま味の味噌に(^-^)
完成にはもうしばらく待ったほうが、更にマイルドな味噌になります。
我が家では、ほぼ一年経った頃から食べ始めています。
2月16日に仕込んで、6ヶ月余り。
糀がイイ仕事ぶりを発揮して、
煮た大豆と塩が、みごとに馴染み味噌に成長しています。
蓋の形状が、軽い圧を加えるので、味噌の熟成を助けるのだそうです。
地元の大豆と塩と米糀で仕込み、
美味しくて安心の味噌を、
毎日の食卓でいただけるのは、佐渡暮らしの幸せ( ^^)
味噌は、仕込みも、その後の管理も簡単ですので、
自分で作る味噌が、もう一度、復活できるといいな‥と思います。
☆。。。。。☆。。。。。☆
毎月、天地かえしをして管理している醤油も、
この日に一緒に、作業しました(^^)/
順調に発酵中のようです。
醤油らしい色と香りも加わってきました。
お味噌も醤油もできあがるまで、もう少しのようです。
熟成を楽しみに待っています。
佐渡国際トライアスロン大会の日は、
(今年は、9月1日でした)
島の人はノーカーdayが定着しています。
その日は、
羽茂川の鮎を、石焼きで味わう日として会員が集まります。
朝9時に、お地蔵さま前の広場に集まり、準備を始めます。
先ず、会場を清め、テントを張るところから。
一番に大切な準備、石を焼きます。
見守る、お地蔵さま。
会員の多くは、幼い頃ここで遊んだ思い出がある広場。
幾つもの石に、味噌と茄子で土手を作り、
うるか(鮎の内臓)を焼きます。
いつも串焼きを担当している方が、
今年は、周りを囲むパネルを作ってくれました。
骨までムラなく、とても香ばしい焼き上がり(^^)/
会員の熱意で、焼きのシステムも年々進化中です。
こんがり、みごとな焼き目がつきました。
竹のコップ、竹串の作品。
丁寧に、呑み口が滑らかに削られていました(^^♪
持ち寄った夏野菜で一品。
山形県では、“だし”と呼ばれる郷土料理だそうです。
茄子ときゅうりを、小さく“さいの目”に切ったものに、
茗荷・生姜・青紫蘇・オクラ・白ごまの煎ったものを加えてさわやかに。
醤油・味醂・酢・砂糖で味付け、馴染ませます。
(本場では、ガゴメ昆布を刻んだものを入れる)
薬味が、それぞれの香りや食感を主張し、楽しめます。
我が家でも真似できる、
夏野菜のおかずメニューを、教えていただきました。
ご飯にたっぷりのせたり・素麺のつけ汁・冷奴などに相性がいいそうです。
さて、ようやく、お料理が並びました。
てんでの者が、何かの役割を担当して完成。
さあ、乾杯 (^-^)
一年ぶりの鮎を楽しみながら、おしゃべりしましょう。
鮎の会では会費を出し合って、羽茂川に鮎の稚魚を放流しています。
(イワナとヤマメの稚魚も、日を変えて同じ頃に放流)
昔は、羽茂川の鮎をヤスで突いたり、投網で漁をしたものだそうです。
それを、河原で石焼きで食べた文化がありましたが、
今では、そうして食べることはほとんどなくなりました。
鮎を食べることは、守らなければ続かない
懐かしい食文化となっているそうです。
石を川から拾って焼くこと3時間、から始めて、
竹で串を削り、漬けものやお酒を持ち寄ります。
賑やかに楽しんだろう、昔の人たちの笑顔が思い浮かびます。
座っていれば、ご馳走が次々と並び、出てくるというような、
どこぞの料亭の鮎料理とは、一線を画した意味を持っています。
せっかく、炭がたっぷりあるのだから‥と、
味噌を付けて、茗荷を焼いてみました。
辛い神楽南蛮も、焼いてみました(>_<)
超~辛かったようですが、楽しそう。
空き缶に入れて、炭の中に埋めてみました。
形を残して、キレイな炭が焼き上がりました(^^)/
鮎の石焼きを体験したいと、帰省して参加したお二人。
東京浅草で、佐渡の食材たっぷりの料理を提供している『だっちゃ』さん。
そうなんです。 店名の『だっちゃ』は佐渡弁です。
「〇〇だっちゃ」「◎◎だっちゃねぇ」
オーナーのさやかさんは、酒匠でもあります。
帰省する毎に、地元の酒蔵をまわり、
蔵元さんと会って、今のお酒の情報を熱心に集めて回ります。
佐渡で活動されている話題の人・観光の現場にも出向き体験もしています。
東京・浅草の「だっちゃ」には、
佐渡にゆかりのある人が多く集まり、
佐渡からの地酒と食材を楽しめる、拠点となっているお店。
先日、佐渡の全部の蔵元のロゴをプリントした
見覚えのある、ポロシャツを着た人にお会いました。
「いいですね。佐渡の酒蔵めぐりをされたのですか?」
お聞きすると、
「あ、わかるんだ。これ、だっちゃのよ」
“だっちゃ”で佐渡のファンになった方が、
観光で佐渡に来て下さったのです!(^^)!
さやかさんのように、足で廻った佐渡情報は新鮮。
一日を一緒に過ごしてみれば、
東京で「佐渡の食や文化を発信中」の
元気で率直なさやかさんの人柄が分かってきます。
頑張っている人には、無条件で応援したい。
佐渡の小父さん達は、いつの間にかさやかさんのファンになったよう。
微笑ましかった ^^)

佐渡の柿餅本舗
2009年秋、佐渡へ移住。
「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。
最近のコメント
アーカイブ
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年