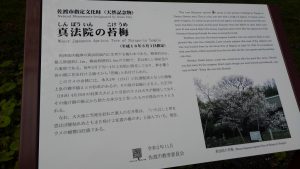- おけさ柿日記
両津への納品の途中に
春の一瞬だけ現れる、雪形の白いキツネが見えました。
翌日は、相川へ
金山の駐車場にて
江戸幕府の財政を支えた、佐渡金山。
金の鉱脈に沿って、人力で露天掘りを続けた結果、山の頂上部がVの字に割れてしまった‥。
佐渡金山のシンボル《道遊の割れ戸》を仰ぎ見ての、桜を訪ねました。
軽やかな花びらや、おだやかなピンクの桜の色は
気持ちを慰め、心を明るくしてくれる不思議な力があるよう。
今年は、用事で出かけた先で、車でスゥーと通りすぎるだけの
ドライブスルーの花見がほとんどでした。
春祭りのない佐渡の、春の1ページが過ぎていきます。
田んぼにトラクターが入り、水が張られてきました。
畑でも、とても忙しそうな人の動きがみえます。
おだやかな陽ざしに誘われて、水芭蕉を訪ねてみました。
元は田んぼだったところに、荒れるよりは花をと、植えられたのだそうです。
ゆずろ公園近く
山の中の、水が澄んだ湿地一面に水芭蕉
「三日前にも来たのよ、
白い花がみごとだったので、今日は友達を誘ってね」
「たった今しがた、朱鷺が鳴きながら飛んで行ったところでね」
「下から見上げたら、羽がとっても美しかった~」
・・・と、楽しそうな二人連れ。
車を降りてから、水芭蕉の沢までの途中には、急な登り坂はありますが
明るくて、迷わずに行ける道があります。
道の傍には、咲き始めたばかりの山野草が可憐にちらほら。
「この奥に、カタクリが咲いていますよ~」
明るく声をかけてくれて、
「ごゆっくりねぇ」と、先に帰って行かれました。
木々の若葉も、少しずつ淡い緑色になりはじめたところ。
葉っぱの形や色も、可愛い芽生えの姿。
どの花も、群れずに一輪。
凛として咲いています。
花の名前や木のことを、もっと知っていればなと思う時です。
今日は、小学校の入学式が行われた佐渡。
我が家では、
冬タイヤから、やっとタイヤ交換をしました。
人気の、羽茂・大崎の種蒔き桜へ
花の色は、白っぽい感じになりましたが
枝の先まで、みごとな花を咲かせています。
ごつごつとして、黒く力強い幹の姿。
古木の少しの傾きと、根本の藁葺の庵が絶妙なバランスの美しさ。
大崎の真ん中で、華やぎを見せています。
一本桜ならではの、大きく逞しい存在感です。
晴れれば、花を求めて。
今日は、両津へ。
梅津の真法院の苔梅を訪ねました。
フェースブックで、友人が教えてくれたのは《苔梅》
幹にはびっしりと苔が覆い、威容を誇っています。
美しい花びらは、淡い紅色の八重。
すぐ近くの羽黒神社まで、醤油造りの箱根清水を汲みに何回も通っているのに、
真法院の苔梅の存在を知りませんでした。
桜花は人を呼び、わたし達の前にも
軽自動車に分乗しての、お母さん方の団体さんが 7 人。
「丁度いい時に来られてよかった~」
「きれいねぇ」
「ここの次は、大慶寺の桜の並木を散歩してから
お昼には、何か美味しいものを食べようと相談しているのよ~」
…と、花めぐり遠足のご様子。
どう見ても、 70 歳をとうに超えていそうな先輩がた。
乙女のように、賑やかで、笑い声が絶えません(^O^)
隣に咲く桜は、地面に触れそうなくらい枝垂れて、揺れています。
盛りの梅と桜が一緒に見られるとは(*^^)v
軽やかな花が目当てで出かけましたが、
幹の太さや傷もコブも、歴史の永さが品格を物語る、
苔梅を知った喜びの日になりました。
陽ざしがぽかぽか。
子供たちは半袖になって、外遊びに夢中でした。
絶好の花見日和なので、ドライブへ。
満開の桜の通り。
ちょっと遠回りでも、桜の下を自転車で走る人あり。
学校には、桜が似合います(^O^)
ここ羽茂川沿いは、歌碑が立ち並んでいる事でも知られている所。
転作と 決めし田の面の 雪解けて 緑かなしく 萌ゆる若草
待ちまちし 春陽したしも おろしたての 地下足袋かるく 野菜畑うつ
短歌を詠む生活が日常としてあり、
農業者としての思いが、スッ~と伝わってきます。
歌碑をたどっての、ゆっくり散策もお薦めのコースです。
すももの古木から、香りが強く漂っています。
藪椿も、甘く香ります。
椿の大木が多い島ですが、ここでは生垣として活躍。
たっぷりの花をつけた、みごとな一本。
事務所の方に、お話を聞くと
雌雄の木を買ったけれど、一本は別の所に植えたため実を付けないそう‥。
「やっぱり一緒に植えた方がよかった‥かな」
「大きな実をつける桜んぼ🍒の苗と聞いたんだけれど」と、(^O^)
ぐるり回って、赤泊へ
明るい、かたまり。
ドライブしてみると、あそにも、ここにも
桜・すもも・辛夷・モクレンなどが、今、花盛り。
納品の帰りに見かけた、白っぽい桜の花
公園でもなく、庭園でもないけれど、
ここかしこに、光を浴びて、
堂々とみごとな花を咲かせている木が多く存在していました。
桜に誘われて出かけ、
花めぐりの楽しい半日になりました。

佐渡の柿餅本舗
2009年秋、佐渡へ移住。
「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。
最近のコメント
アーカイブ
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年