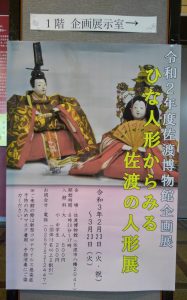- 2021年
今年も朱鷺の巣作りの一号が、確認されたそうです。
朱鷺の子育てが始まりました。
今日、友人からいただいたのは
完熟のシークワーサー。
温室育ちの木から、「好きなだけ実をもいで行ってね」と、もらったそうで‥
そのおすそ分けを、いただきました。
佐渡でもシークワーサーを育てている人がいる !(^^)!
うれしい驚きです。
レモンに似た香りと酸味が、実にさわやか。
もっぱら、焼酎に絞り入れたり、炭酸で割って味わっています。
ミカンのように、皮をむいて食べても美味しい(^O^)
「シー(酸っぱい)」「クワーサー(食べさせる)」の意だそうです。
沖縄では、緑色のシークワーサーが日常使いされているそうですが、
完熟の実は料理に添えると、丁度いいサイズと色あいです。
☆。。。。。☆。。。。。☆
農作業も始まりました。
先ず、水を田んぼに引き込むための《江ぇ掃除、江ぇ上げ》作業から。
人手が揃う日曜日に、共同作業が組まれている集落が多いようです。
田んぼの準備も始まったようで、軽トラを畦道に見かけます。
忙しい季節になって、みなさんが生き生きと活動を始めました。
朱鷺も人も、春を待っていました(^O^)
さあ、いざいざ。 スタートです。
3月7日、三月の初めの日曜日。
大倉谷集落の入口と出口の境目に
「春切 はりきり」という、古くから伝わる風習
高々と“大わらじ”が掛けられました。
何やら、願い事の書かれた木札が付いています。
こんな大男が住む集落では、悪さはできない‥賊は逃げ出すのだそうです。
新しく掛けられた大わらじの傍に、咲き初めたばかりの一枝。
疫病を除け、悪人の侵入を防ぐ道祖神として祀られる、倉谷地区の春の風物詩。
集落のみなさんの共同作業で、大切な行事が伝えられています。
毎年、ちょっとだけ“大わらじの”出来が異なっていて、温かみを感じます。
大わらじの効き目や如ん?
神仏の加護により、効験あらたかなれ(^O^)
春をどれだけ待っていたのか。
陽ざしのこと、暖かさの感じなどを、繰り返しブログに書いていることに気づきました。
今日の温もりと光に、長かった冬からの解放感(^^)/
背筋が伸びて、気持ちも明るくなってきます。
☆。。。。。☆。。。。。☆
今年は、お雛様を飾ってあるお宅を訪ね、街歩きを楽しむ雛祭りの催しが無くなりました。
雛まつりを祝っての、《ひな様まんま》や《雛さま御膳》などの、
特別な食事も、計画がありません。
相川・小木・岩谷口などの雛まつりは、春の楽しみなのですが‥(>_<)
佐渡博物館で、ひな人形の企画展が開かれていますので寄ってみました。
古いお雛様らしい、お顔と衣装
たくさんの人形やお道具が、吊るし雛に。
産まれてきた子どもの幸せを願って(^O^)
小さな一つひとつの飾りに、思いがこもっています。
江戸時代~明治にかけて日本海航路には北前船が行き交い
佐渡は、活況を呈した時代がありました。
金山の開発によって直轄地となった佐渡に、全国各地から人や物資が運ばれました。
ひな人形を飾るのは、限られた家々ではありましたが、
上方の享保雛、江戸で流行った古今雛で祝う風習が伝えられた由。
その以前には土で人形を作り、地方の農村では子供の成長を祈ったそうです。
我が家の小さなお雛さまを飾って、春を祝っています。
お雛さま、
柿餅本舗の特製《めでたいおかき》を
ど~ぞ (^O^)
ひな人形の企画展は、3月23日(火)まで、開催されています。
日毎に、陽ざしが明るくなっています。
今朝は、早起きの雀に起こされました。
☆。。。。。☆。。。。。☆
佐渡番茶で、《茶粥;ちゃげー》
濃い目に煎じた番茶で、土鍋でお米を炊きました。
20分くらいかけて、吹きこぼれない程度の強火で炊きます。
たっぷりの番茶を煮出した中に、洗ったお米を入れ、
煮始めは、底にお米がくっつかないように、
何回か、木べらで回します。
梅干し 塩昆布 鮭 紫葉漬け を、添えていただきました。
さらさらとした《茶粥》は 香ばしい番茶の香り。
上横山産の佐渡番茶は、一番茶も二番茶も一緒に焙じたお茶ですので、
甘さも香りも爽やかな渋味も、ぜ~んぶが美味しく味わえます。
お茶の生産農家さんが、毎日食べている《茶げ~》
昔から食卓に伝わる、佐渡の食文化。
とってもやさしい茶粥は、
心も体も
あったまりま~す(^O^)/
パラパラと雪が降り、白い世界が広がったり安定しない一日でした。
畑の隅には福寿草が一輪咲いて、光を集めています。
ここにも、小さい春。
まぶしい(^O^)/
☆。。。。。☆。。。。。☆
金鶴さんの、風和(かぜやわらか)のしぼりたて生、を一本。
塩麹を仕込もうと《金鶴の麹》を、求めてきました。
この麹で、以前に甘酒を作った時には、
クリアな味で、とてもなめらかな味でしたので。
今度は、
もち米入りの塩麹を仕込んでみました。
もち米を炊いて、麹の働きを妨げない温度 60℃くらいまで、
少し冷ましてから、麹と塩を混ぜ合わせます。
およそ、一週間ほどの間、毎日混ぜあわせれば塩が馴染んできます。
雑菌の少ない《寒》に仕込むのがベストだそうです。
餅米と麹のダブルの米が、自然な甘さを醸してくれます。
餅米入りの塩麹で、野菜を漬けていただくのが楽しみ。
カブ きゅうり 茄子 大根 人参など‥色よく、美味しく漬かります。
野菜の炒め物に少し入れても、旨味が加わって⤴⤴
友人は、醬油に麹を加えて《醤油麹》を作り
野菜を漬けたり、魚や肉の下味付けすると
「とってもおいしいよ~」と、教えてくれました。
酒蔵 金鶴さんの《麹》 大活躍です!(^^)!

佐渡の柿餅本舗
2009年秋、佐渡へ移住。
「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。
最近のコメント
アーカイブ
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年