- 2019年
今日は冬の晴れ間。 ぽっかりと、明るい陽ざしに恵まれました。
私達は、雑菌の活動が少ない冬場の大切な作業として、寒中に味噌の仕込みを毎年続けています。
その原材料となるのは、佐渡産の大豆と米麹と塩。
佐渡で、“ 古き時代からの食養・農法 ” を実践して、自然栽培をしている
“ いつくの郷 ”の笈川さんご夫婦が、
味噌の仕込みのための、大豆と米麹を届けて下さいました。

大豆 糀
自然栽培 ( 無肥料無農薬 ) 大豆 サトウイラズ と ササニシキに糀を付けたもの。
家族の食卓には、安心な野菜や調味料で作ったものをのせたい(^u^)
私たちは作れるものはできるだけ、自分で作りたいと思っています。
志ある生産者さんが近くにいる、田舎暮らしなればこそできることがあり、
その幾つかが、味噌・醤油を作ることです。
“ いつくの郷 ” さんは、主義ある農業に取り組んでいる農家さんで、
自給自足を目指して農業を始められて、およそ10年目とか。
自給率は目標の3割ほどのところまで、達成できたそうです。
私たちはこの安心素材で、自分で作る味噌・醤油を作りを楽しんでいます。

大豆 サトウイラズで味噌作り
砂糖いらずとも麹いらずとも呼ばれる、旨さの濃い緑色の大豆。
収穫量が少ない、貴重な大豆です。

ササニシキ 米麹
ササニシキに “ 塚本糀店 ” さんの麹を付けた米麹。
ぜ~んぶ佐渡産の味噌(^u^)
これは、自家製の醤油作りの一コマ。 定期的に醤油の天地返しをしています。

自家製の醤油作り
この自然栽培のエゴマや黒米≪朝紫≫で、我が柿餅本舗の製品を作り、
「 新潟県のうまいものセレクション」にも、選ばれています(^_^)v
エゴマを餅について「えごまのおかき」を。

えごま

エゴマのおかき
古代米・朝紫で、「古代餅」を。

黒米 古代米 朝紫

佐渡の古代餅
ベースとなる、おいしい餅米 ( こがねもち ) も、もちろん佐渡産(^u^)
佐渡の「朱鷺と暮らす郷づくり認証制度」のもとで栽培された、もち米 “ こがねもち ” と、
無農薬・無肥料で自然栽培された貴重な安心素材の、大豆・えごま・古代米 ( 朝紫 ) で、
佐渡の柿餅本舗は、地元のこだわり原材料を生かした安心安全な素材で、
美味しいお餅とおかきを作る。
生産者さんの上質な素材を努力して探すことは、
美味しい製品を作ることへの、大切な第一歩と考えています。
鶏のコッコちゃんと山羊のメェ~さんとの暮らしのブログ
いつくの郷 さんのHPはこちらです。
http://www.itsukuno-sato.com/product.html
夜の間中、強く風が吹きすさびました。
クロ猫さんに、荷物を持ちこむ予定にしていますので、
今日は出航できるのか? 欠航になるのか? 佐渡汽船が運行されるのか気になります。
こんな日は、家に籠もって家にあるもので、メニューを考えることにしました。

納豆汁
佐渡の畑で育てた大豆で作られた “ トキ納豆 ”
すり鉢でなめらかになるまで、擂りつぶします。
味噌汁の具には、冬の保存野菜の白菜・大根・人参・里芋など‥何でも(^u^)
それに加えて、打ち豆も入れるとダシの味が深まります。

納豆汁
納豆 + 打ち豆 + 味噌と、大豆・豆・豆とマメだらけ。
納豆を擂り、味噌の色と、ビジュアル的には地味~な汁椀に見えます。
ですが‥滋養たっぷりで、体が温まる冬のご馳走。
すり鉢を持ち出して、打ち豆を入れて‥
手間のかかった
昔ながらの納豆の味噌汁など、食卓に上らなくなりました。

お稲荷さん 納豆巻き
豆づくしのメニューとして、納豆巻きとお稲荷も。
お稲荷さんの中には、梅紫蘇漬けのタケノコ・茗荷。赤カブの葉を刻んで入れて\(^o^)/
美味しいものは、<畑> にあります (^_^)v
朝から、強い勢いで雪が降っています。
防寒対策をしっかりして、新年初めての、おとなの遠足へ出かけてきました。
沢根質場の崖をジオパークをガイドと歩き、元二見集落までのコース。

準備体操
いつものように、ウォーミングアップして、出発。

沢根崖
佐渡の地層の成り立ちを、ジオパークガイドさんの説明をお聞きました。
シマシマの地層がすぐ側で見える、沢根質場層は脆い砂が堆積した地層。
以前に「島の新聞」で、この沢根質場を真横に横切る、
北緯38度線を取材したことがありますが、
今回は、この地層の4段の段丘地形のことや砂泥互層のことなどを中心に見学(^_^)v
てくてく

長安寺 長屋門
直江兼続が、佐渡へ上陸した地と伝えられている寺。
沢根城主に(武士の身分)を許されて、漆喰壁の長屋門を持つ寺となったそうです。
ご住職に、いわれを伺いました。

長安寺にて
続いて、羽二生集落を抜けて曼荼羅寺へ。
途中で、朱鷺3羽とも遭遇\(^o^)/

小休止
てくてく 二見新町の家並見学へ

二階がせり出している家並
昔の花街の名残りを伝える、出桁造りの古い町並み。
二見の郵便局のトイレをお借りしたり、海運で栄えた旧家を拝見したり。

二見神社
150段の石段を上り、お参り。
もう少し足を伸ばして、元二見集落へ。

八房の梅
春にはどんな花を咲かすのか?
すぐお隣には、小さな神社が。

事毘羅神社
地域のみなさんに、大切に守られています。
以上、ここで昼食会場の迎えの車を待って、おとなの遠足終了。
今日は、11.500歩の遠足となりました。
続いて、新年会会場の浦島さんへ。

新年会 浦島さんにて
おとなの遠足の新年会。 参加者は40名ほど。
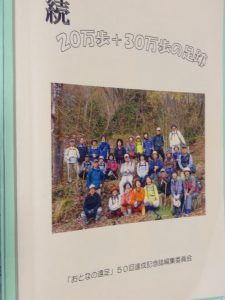
第二冊目の 足跡
「 おとなの遠足 」 50回達成を記念して、第二冊目の記録冊子も発行されました。
毎回、下見をし、内容の充実した計画を立てて下さる方がいての「おとなの遠足」です。
参加者も増えてきているそうです。
私たちは、昨年9月、51回めからこの会に参加させていただき、
たくさんの仲間と一緒に、歩くことの楽しみに気づかされました。
あの人この人、たくさんの仲間に感謝します。
先ほどから、いよいよ嵐。
西からの風が大きな音をたてて、佐渡の平野部を真野湾から両津湾へ吹き抜けていきます。
佐渡は風の島を、実感する冬です。
地元の魚を揃えてある鮮魚店が近くにあって、
季節ごとの今のお薦めや、料理の仕方・下ごしらえの仕方を教えてもらっています。

するめいか大根
お店に寄ってみると、今日は大きくて身の厚いスルメイカがありました。
迷わず、大根と組合わせて煮ようとメニュー決定 (^O^)

アオリイカ 塩辛
身が厚く、食感がもっちり
季節ごとにお店の特製、手作りアオリイカ・ヤリイカ・スルメイカの塩辛が選べます。
塩のアンバイが程よくて、常備食として我が家の食卓に出番あり。

あおりいか 一夜干し
「今は、アオリイカの一汐干しも美味しいですよ~」とのことで (^_^)v
身が厚くて、旨みと甘さが濃縮されています。

スルメイカ
イカ・タコが好きな我が家は、刺身でよし、焼いてよし。
今日もイカづくしの食事。
晩酌のお供に、いただきま~す。
畑で育てたハブ茶を、昨年の11月の末に刈り込み、小屋で乾燥させていました。
サヤを割って、豆を剥かなければと思いつつも、
なかなか作業が出来ないでいました。
根気仕事ゆえ、
今日やっと‥重い腰をあげて、取り組みました\(^o^)/

ハブ茶
この後、きれいな豆と未熟な豆とを選り分けて、完成。
軽く炒ってから、少量ずつ他のお茶とブレンドして、
クセの無い飲み口のお茶にして、楽しんでいます。
漢方では決明子(ケツメイシ) とも呼ばれる、マメ科の植物。
眼精疲労や便秘にも効果があると知られ、お茶として飲まれるのがハブ茶。
6・7 年前、たまたま佐渡旅行を楽しまれた方からいただいたハブ茶の種を、
私達は、大切に育て続けています。

ハブ茶
日本では南の地方のほうが育ちやすいようで、
佐渡では、GWを過ぎて地温が上がってから種を蒔くと教えていただきました。
連作の障害もあるようで、畑の中を移動しながら植えています。
雑草にも強く、世話なし、肥料もなしで育つ丈夫な植物です。

決明子 (ハブ茶)の花 10/5
豆だけでなく、
写真の頃に葉っぱを刈り取り、干してから焙じてお茶にもする方法もあるようです。

ハブ茶
今年も無事に収穫できました(^-^)
数人の友人にも種をお分けして、育てていただいています。

佐渡の柿餅本舗
2009年秋、佐渡へ移住。
「佐渡の特産を使い、昔から食されてきた柿餅を、佐渡のお菓子として多くの人に知ってもらいたい」という想いから、商品化に乗り出しました。
最近のコメント
アーカイブ
- 2025年
- 2024年
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年


